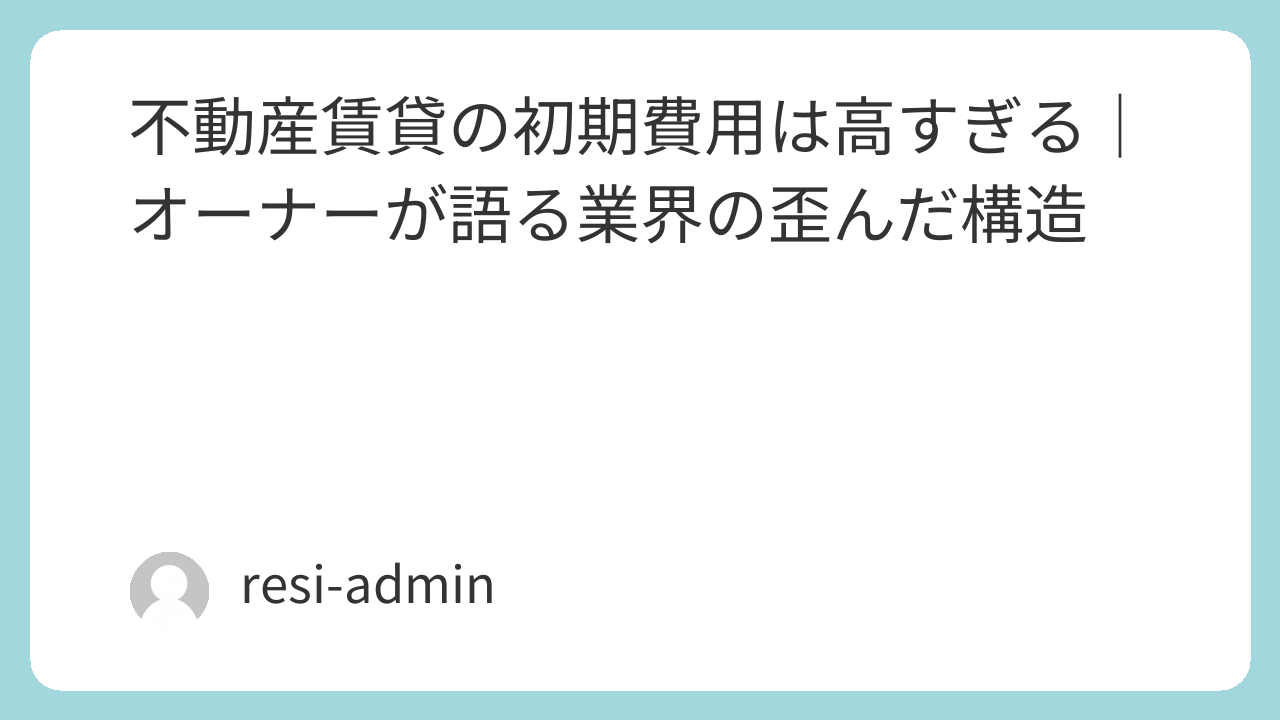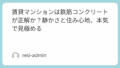賃貸マンションのオーナーとして、率直に言わせてください。今の日本の賃貸市場における初期費用は、明らかに高すぎます。
家賃6万円の部屋を借りるのに30万円から40万円必要という現実を、誰も疑問に思わなくなっている。これは異常です。
この記事では、賃貸業界に身を置く人間として、初期費用が高すぎる問題の本質と、その背後にある業界の構造的問題について、忖度なく語ります。
初期費用が家賃の5〜6ヶ月分という異常事態
賃貸物件を借りる際の初期費用は、一般的に家賃の5〜6ヶ月分と言われています。これがどれほど異常な金額か、具体的に見てみましょう。
初期費用の内訳例(家賃6万円の場合)
- 敷金:6万円(家賃1ヶ月分)
- 礼金:6万円(家賃1ヶ月分)
- 前家賃:6万円(入居月の翌月分)
- 日割り家賃:3万円(月半ばの入居として)
- 仲介手数料:6.6万円(家賃1ヶ月分+消費税)
- 保証会社利用料:3〜5万円
- 火災保険料:1.5〜2万円
- 鍵交換費用:1.5〜2万円
合計:33〜39万円
これは新卒社員の初任給(約20万円)の1.5倍から2倍にあたる金額です。
世界的に見ても異常に高い
海外の賃貸市場と比較してみましょう。
- アメリカ:敷金1〜2ヶ月分のみが一般的
- イギリス:デポジット(敷金)1〜2ヶ月分
- ドイツ:敷金最大3ヶ月分(礼金は存在しない)
日本の5〜6ヶ月分という初期費用は、明らかに国際標準から外れています。
若者の引越しを阻害している
初任給20万円の新社会人が、40万円近い初期費用を用意するのは極めて困難です。結果として何が起きるか。
- 実家から通える範囲の就職先しか選べない
- 転職したくても引越し費用がネックになる
- 労働市場の流動性が下がる
- 地方の若者流出が加速する
初期費用の高さは、単なる個人の問題ではなく、社会全体の問題なのです。
礼金という名の「意味不明な慣習」
初期費用の中で最も理解不能なのが「礼金」です。オーナーとしては正直これが無くなるのは痛いのですが、正直に言います。
礼金ほど意味のわからない項目はありません。
礼金の建前と実態
- 建前:「部屋を貸してくれてありがとう」というお礼の気持ち
- 実態:「貸してやるから金よこせ」という上から目線の慣習
「お礼」なのに返ってこない。これがおかしいと思いませんか?
礼金が生まれた時代背景
礼金が生まれたのは、戦後の住宅不足の時代です。
- 借りたい人が殺到していた
- 大家は「貸してやる」という立場だった
- 借主が「ぜひ貸してください」とお願いする関係
しかし今は2025年です。全国的に空室率は上昇し、借主を探すのはオーナーの方です。立場は完全に逆転しています。
なぜ今も礼金が残っているのか
理由は単純です。「昔からそうだから」。これだけです。
誰も疑問に思わず、慣習として続いている。オーナー側も「取れるものは取っておこう」という発想で、礼金を設定し続けています。
オーナーとしての本音
正直に言えば、礼金なんて要りません。入居してくれるだけでありがたい。空室期間が長引く方がよっぽど損失です。
礼金ゼロにすれば入居が決まりやすくなり、結果的にオーナーも得をする。なのに、業界の慣習に従って礼金を設定している物件が多いのが現実です。
仲介手数料は「情報の非対称性」に対する対価なのか
仲介手数料は家賃1ヶ月分+消費税が一般的です。家賃6万円なら6.6万円。この金額に見合った価値があるのでしょうか?
仲介会社がやっていること
- 物件の紹介
- 内見の立ち会い
- 契約書の作成と説明
- 鍵の引き渡し
これで6.6万円。時給換算すると、どれだけ高額な対価なのか分かるでしょう。
かつては価値があった
インターネットが普及する前、仲介会社には確かに価値がありました。
- 物件情報を独占していた
- 借主は仲介会社に行かないと物件を知ることができなかった
- 情報を持っている者が強かった
この「情報の非対称性」に対する対価として、仲介手数料は正当化されていました。
ネット時代における仲介会社の役割
今は誰でもスマホで物件情報を検索できます。SUUMOやHOME’Sを開けば、写真も間取りも設備も一目瞭然です。
では、仲介会社は何をしているのか?
- 内見の日程調整と立ち会い(30分〜1時間)
- 契約書の作成(テンプレートに情報を入力するだけ)
- 重要事項説明(マニュアル通りの説明)
これで6.6万円。コストパフォーマンスが見合っているとは到底思えません。
オーナー直募集なら仲介手数料はゼロ
オーナーが直接募集すれば、仲介手数料は一切かかりません。契約書の作成も、今は管理会社やオンラインサービスで簡単にできます。
仲介会社を通さないと契約できないわけではないのです。
保証会社の利用料 – 誰のための「保証」なのか
保証会社の利用料も、初期費用を押し上げる大きな要因です。しかし、よく考えてみてください。これは誰のための保証なのでしょうか?
保証会社の役割
- 借主が家賃を滞納した場合、オーナーに代わりに支払う
- オーナーの家賃滞納リスクを軽減する
つまり、保証会社はオーナーのリスクヘッジです。オーナーが得をする仕組みなのです。
なぜ借主が払うのか
これが最大の矛盾です。
- オーナーのリスクを減らすための保証なのに
- 費用を払うのは借主
- 初回:家賃の50〜100%(3〜6万円)
- 更新料:年1万円程度
借主にとって何のメリットもありません。にもかかわらず、ほぼ強制的に加入させられるのです。
敷金があるのに保証会社も必要?
さらに矛盾しているのが、敷金と保証会社の両方を求められることです。
- 敷金:家賃滞納や原状回復費用に充当できる
- 保証会社:家賃滞納に備える
両方とも同じリスクに対する備えです。二重取りではないでしょうか?
管理会社と保証会社の癒着構造
なぜ保証会社の利用が強制されるのか。理由の一つは、管理会社と保証会社の関係です。
- 管理会社は保証会社を紹介することで手数料を得る
- 保証会社は管理会社から顧客を紹介してもらう
- Win-Winの関係(ただし、借主を除く)
結局、借主だけが損をする仕組みになっているのです。
「分割払いサービス」は問題を解決していない
最近、「ゼロスム」や「Smooth」といった初期費用の分割払いサービスが登場しています。「借主に優しい」という触れ込みですが、本当にそうでしょうか?
分割払いサービスの仕組み
- 初期費用を0円または少額に
- 毎月の家賃に分割した金額を上乗せ
- 手数料が発生する
確かに、一時的な負担は減ります。しかし、これは本質的な解決なのでしょうか?
「払えない人を助ける」のか「払えない人から手数料を取る」のか
分割払いサービスは、こう謳います。
「初期費用が払えなくて困っている人を助けたい」
しかし、実態は違います。
- 初期費用30万円を24回払いにすると、手数料込みで総額35万円に
- 5万円の手数料は誰の利益になるのか?
- 「助ける」のではなく「ビジネス」をしているだけ
本質的な問題は放置されたまま
分割払いサービスが広まることで、何が起きるか。
- 初期費用が高いままでも「分割すれば払える」という言い訳ができる
- 業界は初期費用を下げる努力をしなくなる
- 結果的に、初期費用の高さが固定化される
本当に必要なのは「初期費用を下げること」であって、「払い方を変えること」ではありません。
分割払いサービスは、初期費用の高さという問題を解決していない。むしろ、その問題を前提にした新しいビジネスモデルなのです。
ポータルサイトという「見えない壁」
初期費用が安い物件を探そうとしても、なかなか見つからない。その理由の一つが、大手ポータルサイトの構造です。
ポータルサイトは「広告プラットフォーム」
SUUMOやHOME’Sは、一見すると中立的な情報提供サイトに見えます。しかし実態は違います。
- 不動産会社が掲載料を払って物件を掲載する
- 掲載料は月額数万円〜数十万円
- つまり、ポータルサイトは「広告プラットフォーム」
掲載料を払えない物件は存在しないも同然
ここで何が起きるか。
- オーナー直募集の物件は掲載料を払わない(払えない)
- 敷金・礼金ゼロで家賃も安い物件は、広告費をかける余裕がない
- 結果、ポータルサイトには表示されない
つまり、本当に条件の良い物件ほど、検索に出てこないのです。
借主は「選ばされている」
ポータルサイトで物件を探すとき、私たちは「自分で選んでいる」と思っています。しかし実際は違います。
- 表示されるのは広告費を払った物件だけ
- 選択肢はあらかじめ絞り込まれている
- 「選んでいる」のではなく「選ばされている」
ポータルサイトに頼る限り、初期費用は下がらない
ポータルサイトに掲載料を払える物件とは、つまり初期費用が高い物件です。
- 仲介手数料を取る → 仲介会社が儲かる → 広告費を払える
- 敷金・礼金を取る → オーナーの収益が高い → 広告費をかけられる
逆に言えば、初期費用を抑えた物件は広告費を払う余裕がなく、ポータルサイトには掲載されないのです。
初期費用が高い本当の理由
ここまで個別の問題を見てきましたが、初期費用が高い本当の理由は何なのでしょうか。
業界全体が「初期費用の高さ」で成り立っている
初期費用が高いのは「仕方ない」からではありません。そう設計されているからです。
業界全体の利益構造を見てみましょう。
- ポータルサイト:掲載料で儲かる(月数万円×全国の不動産会社)
- 仲介会社:仲介手数料で儲かる(物件1件につき家賃1ヶ月分)
- 管理会社:保証会社への紹介料で儲かる(契約1件につき数千円〜数万円)
- 保証会社:保証料で儲かる(契約時+毎年更新料)
すべての関係者が、初期費用が高ければ高いほど儲かる仕組みです。
借主だけが損をする
この構造の中で、唯一損をしているのが借主です。
- 高い初期費用を払わされる
- 選択肢が限られている
- 情報が偏っている
そして、多くの借主は「これが普通」だと思い込んでいます。
オーナーも実は被害者
実は、オーナーも完全な勝者ではありません。
- 高い初期費用は入居のハードルを上げる
- 入居が決まりにくくなる
- 空室期間が長引くリスクが高まる
初期費用を下げれば入居しやすくなり、空室リスクも減る。オーナーにとってもメリットがあるのです。
変わらないのは「変える気がない」から
では、なぜこの構造は変わらないのか。
答えは単純です。変える気がないからです。
- 既存のプレイヤーは今の仕組みで儲かっている
- 変革する動機がない
- 借主の無知と諦めが、この構造を支えている
借主が取るべき行動
では、借主は何もできないのでしょうか? いいえ、できることはあります。
「これが普通」を疑う
まず最初にすべきことは、思考停止をやめることです。
- 初期費用が家賃の5倍は普通ではない
- 礼金は必須ではない
- 仲介手数料ゼロの物件もある
「みんなが払っているから」「仕方ない」と諦めた瞬間、業界の思うツボです。
ポータルサイトだけに頼らない
大手ポータルサイトは便利ですが、それだけでは本当に良い物件は見つかりません。
- オーナー直募集サイトをチェックする(ウチコミ!、自ら賃貸など)
- 地域の掲示板やSNSを活用する
- 気になるエリアを歩いて「入居者募集」の看板を探す
手間はかかりますが、初期費用を10万円以上節約できるなら、やる価値はあるはずです。
敷金・礼金ゼロ物件を積極的に探す
敷金・礼金ゼロ物件は、決して「訳あり」ではありません。
- オーナーが早く入居者を決めたい
- 空室期間を短くしたい
- 競争力を高めたい
こうした合理的な理由で設定されています。むしろ、借主思いの物件と言えます。
文句を言いながら払うのは業界を延命させているだけ
多くの人が「初期費用高すぎる」と文句を言いながら、結局は払っています。
これは業界にとって最高の状況です。
- 文句は言うが、払ってくれる
- 変革の圧力にならない
- 現状維持ができる
本気で変えたいなら、選択を変える必要があります。
借主一人ひとりの選択が業界を変える
もし多くの借主が、
- 初期費用の高い物件を選ばなくなったら
- オーナー直募集や敷礼ゼロ物件を選ぶようになったら
- ポータルサイト経由ではない物件を探すようになったら
業界は変わらざるを得なくなります。
一人ひとりの選択は小さいかもしれません。しかし、それが積み重なれば、市場は動きます。
まとめ
初期費用が高すぎる問題は、個人の努力だけでは解決できない構造的な問題です。
- 礼金という時代遅れの慣習
- 情報の非対称性を利用した高額な仲介手数料
- 借主が負担する保証会社の利用料
- 問題を解決しない分割払いサービス
- 広告費を払える物件しか表示されないポータルサイト
これらすべてが、業界全体の利益を優先し、借主の負担を増やす構造になっています。
しかし、諦める必要はありません。
賢い選択をすることで、初期費用を大幅に抑えることは可能です。「これが普通」という思い込みを捨て、情報の取り方を変え、本当に自分にとって良い物件を探しましょう。
オーナーとして、この歪んだ構造を変えたい。そのためには、借主の皆さんが声を上げ、選択を変えることが必要です。
業界の「当たり前」を疑い、本当に自分にとって良い選択をしてください。